 |
| DBMの写真(左側の部品) <注:右側はVCO> |
私は電子工作のミキサー回路には、よくDBMを使います。DBMとは、Double
Balanced Mixer の略です。その動作原理を、詳しくここでご紹介しましょう。最近は、一時高嶺の花であったDBMも安価に入手できるようになったため、このDBMをうまく使いこなすとミキサー回路の設計が簡略化でき、かつ高性能化できます。DBMは非常に特性がよく、広い適用範囲をもつミキサーであり、DBMは局発のレベルや、入出力インピーダンスをマッチさせさえすれば、ミキサーのすべてをDBMに替えることができるといえるほどです。DBMには、まだなじみのない方も多いでしょうが、使い方を理解すると、スペアナだけではなく、ありとあらゆる周波数変換回路に応用できると思いますので、ぜひDBMの使い方のノウハウを修得してください。
 |
| DBMの写真(左側の部品) <注:右側はVCO> |
![]() DBMの構造
DBMの構造
DBMは図1に示すように、2つの位相分配器(T1,T2)と4つのダイオード(D1〜D4)から構成され、3つのポート(端子対)を持っています。ポート(1)と(2)の構成は同じです。
 |
| 図1. DBMの概略構造図 |
![]() DBMの動作(その1)
DBMの動作(その1)
図2(a),(b)のように、ポート(1)に大きな交流信号を加えた場合を考えます。
このとき、電流はダイオードを通じて流れますが、電流の流れる経路は加える交流信号の極性により(a)と(b)に分かれます。ポート(1)がプラス側の時が図2(a)、マイナス側の場合が図2(b)になります。
青色の線が、ちょうどポート(1)の信号の流れになっています。すなわち、ポート(1)がプラス側の時、信号は位相分配器T1を介して、D1、D2という経路をたどります。このとき赤色の線、D3,D4には電流が流れません。また、ポート(1)がマイナス側の時、信号は位相分配器T1を介して、D3、D4という経路をたどります。このとき赤色の線、D1,D2には電流が流れません。
ここで、ポート(3)に小さな信号があったとします。図2(a)の場合、小さな信号は、まず位相分配器T1で分配され、それぞれD1とD2を通り、T2の中点を通ります。このとき、小さな信号は位相分配器T2を介してポート(2)へ出力されます。
図2(b)の場合、小さな信号は、まず位相分配器T1で分配され、それぞれD3とD4を通り、T2の中点を通ります。このとき、小さな信号は位相分配器T2を介してポート(2)へ位相が反転して出力されます。ポート(2)に大きな信号を与えた場合も、これと全く同じ動作になります。
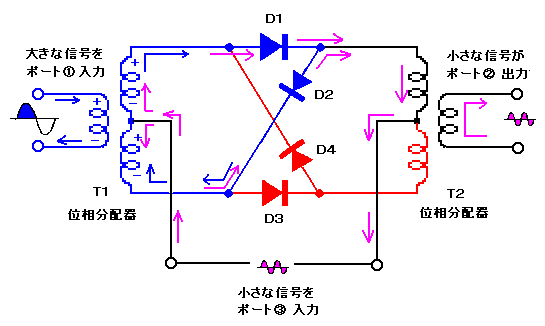 |
| 図2(a). DBMスイッチング動作 1−(a) |
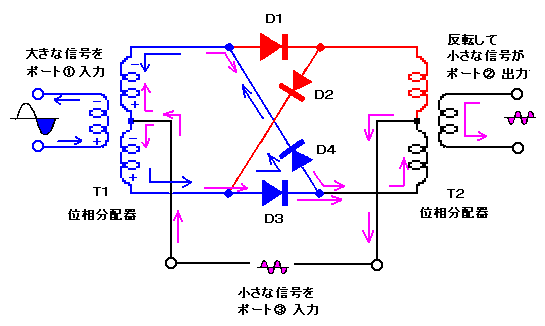 |
| 図2(b). DBMスイッチング動作 1−(b) |
![]() DBMの動作(その2)
DBMの動作(その2)
図3(a),(b)のように、ポート(3)に大きな交流信号を加えた場合を考えます。
このとき、電流はダイオードを通じて流れますが、電流の流れる経路は加える交流信号の極性により(a)と(b)に分かれます。ポート(3)がプラス側の時が図3(a)、マイナス側の場合が図3(b)になります。
青色の線が、ちょうどポート(3)の信号の流れになっています。すなわち、ポート(3)がプラス側の時、信号は位相分配器T1を分配して、D1とD3、T2の中点という経路をたどります。このとき赤色の線、D2,D4には電流が流れません。
また、ポート(3)がマイナス側の時、信号は位相分配器T2の中点で分配して、D3、D4、T1の中点という経路をたどります。このとき赤色の線、D1,D2には電流が流れません。
ここで、ポート(1)に小さな信号があったとします。図3(a)の場合、小さな信号は、まず位相分配器T1を介して、D1、T2、D3を通ります。このとき、小さな信号は位相分配器T2を介してポート(2)へ出力されます。
図3(b)の場合、小さな信号は、まず位相分配器T1を介し、D4、T2、D2を通ります。このとき、小さな信号は位相分配器T2を介してポート(2)へ位相が反転して出力されます。
 |
| 図3(a). DBMスイッチング動作 2−(a) |
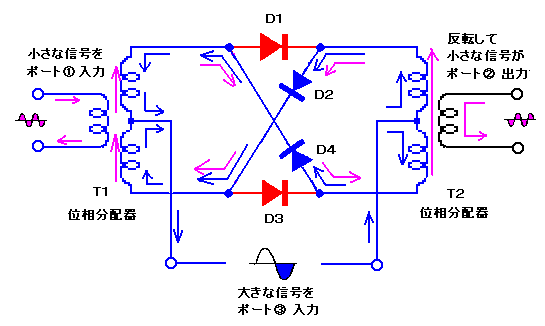 |
| 図3(b). DBMスイッチング動作 2−(b) |
以上のことから、ダイオードがスイッチとして動作していることが分かると思います。
小さな信号を与える端子ですが、それぞれ入れ替えても成り立ちます。たとえば、ポート(1)に大きな信号を加えたとき、ポート(2)とポート(3)はどちらを入力としても、信号を他方へ出力することが出来ます。ポート(2)とポート(3)は、ポート(1)に大きな信号を入れて、ダイオードをONすることにより、相互に接続されるためです。
![]() DBM動作のまとめ
DBM動作のまとめ
どのポートを用いるかにかかわらず、DBMに大・小の2つの信号を与えると、第3のポートに大きな信号の極性に応じた、図4に示すように小さな信号の極性が切り替わるものが出力されます。これは、2相のPSK変調(Phase Shift Keying)の出力波形と同じです。
 |
| 図4. DBMの入出力信号波形 |
DBM出力信号の周波数成分は、図5のようになります。
大きな信号の周波数を f0、小さな信号の周波数を f1としたとき、2通りが考えられます。
(a)が f1>f0のとき、(b)が f1<f0のときです。
破線の成分は出力に現れないことを示しており、いずれの場合にも、加えた元の周波数成分は出力に現れず、2つの周波数の和と差の成分が出力端子に現れ、周波数の変換がなされていることが分かります。また、加えた元の周波数成分が出力に現れないことは、アイソレーションを持っているといえます。
 |
| 図5. DBMの出力スペクトラム例 |
DBMは、ダイオードと位相分配器とを組み合わせた受動回路なので、アクティブなミキサーICと比較して、高い周波数での寄生発振などの不安要素は全くありません。
 |
|
 |